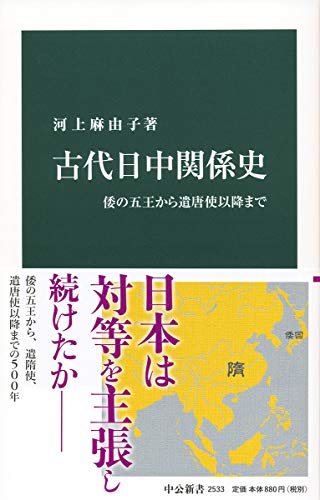江戸時代以前の日本にとって、中国は大国であり、憧れの対象であり続けた。古代から近世まで、中国の文物が貴顕……に熱狂的に受け入れられたことは、大国中国への憧憬を端的に物語っている。
しかし、日本は古代のある時期以降、中国と対等の関係を築き、それ以降は中国を単純に大国とみなすことはなかったという説が根強くある。
それは607年に派遣された日本の遣隋使が、隋(581~618年)の煬帝(在位604~618年)に送った書状の書き出し、「日出ずる処の天子、書を日没する処の天子に致す」……を主たる根拠にするものである。「日出処」とは日本、「日没処」とは隋を指す。両国の君主に同じく「天子」の称号を用いるからには、日本は両者が対等であると主張したに違いないというわけである。……
では、実際には古代の日本は、中国をどのように認識し、どのような交渉を行ったのか。本書は、大国中国の存在を常に身近に感じていた古代の日本が、いかなる手段・方針・目的をもって中国と交渉したのかを実証的に描いている。それにより、先の「常識」とは異なる姿がみえてくるだろう。
例えば5世紀の銘文に現れる「天下」なる語の解釈をめぐる学説の対立が紹介される。片や「広義の天下」、すなわち「民族・地域を超えた同心円状に広がる世界」、片や「狭義の天下」、すなわち「中国を取り巻く四つの大海により限界づけられた封鎖的空間ととらえ、強力な統治権下にある『国民国家』概念だとする考え方」、そして本書でも日中のテキストを交えた吟味が展開される。そんな風に聞けば、また例の象牙の塔の内部でしか通じない議論のための議論か、と嘆息する向きもあるかもしれない。
ところが本書は、そんな言いがかりとはほぼ無縁のスリルの塊。政争といっても今日の小賢しいコップの中の嵐とはスケールがあまりに違う、謀殺、失脚、島流しなんて朝飯前で、何せ本当に体制が覆るシーンが次から次へ描き出されるのだから、これで寝落ちようはずがない。
そしてこの海を股にかけた冒険活劇ロマンでは、登場人物のそれぞれが歴史にひたすら翻弄される。
例えば鑑真、教科書で知らされる情報といえば、唐招提寺の建立と例の彫像くらいのものか、ところがその訪日をめぐっても壮絶なドラマが展開されていた。乞われて海を渡ることを決意し、それが実現されるまでにかかった年数は実に11年、その間5度の失敗を重ねる。そして此度も併せて薦められた道士の招聘がネックとなり――社交辞令を先方が真に受けるというよくある話――一旦は申し入れを取り下げる、密航を企てるも唐に漏れて頓挫、結局は別の船に乗り込んで晴れて日本の土を踏む。
あるいは最後の遣唐使のひとり、円仁の場合。イナゴの害に悩まされる斜陽の唐を巡り歩くこの僧侶は、立ち寄る先で糧をねだるもかなわず、その恨みを日記にひたすらしたためる。長安の寺で迎えた西暦840年の冬至節、祝いの日に辛うじて提供されたものと言えば、粥とスイトンと果物だけ。わびしい食卓を記録するその筆致が、千年の時を隔てて、後世の叙述に血肉をもたらそうとはまさか知る由もない。
こんな悲哀が至るところで惜しげもなく圧縮される、空想がここまでのディテールを配することはかなわない、史実が創作物を凌駕していく。
一国についてしか知らない者は、実はその一国についてすら知らない、と言ったのはアレクシス・ド・トクヴィルだったか。
本書においても、この碩学による箴言の圧倒的な真実味を突きつけられる、すなわちそれは「日本」という国号の由来において。
かつては、太陽の昇るところを意味する「日本」を国号に用いたのは、唐に対する対等、ないしは優越を主張するためであったと論じられることがあった。
この通説を覆す史料が、近年中国で発見された。百済祢軍の墓誌である。……
さてこの祢軍の墓誌には、「日本」が百済を指して用いられている。墓誌は唐で作制されたものであるから、「日本」という語の用方は、当時の中国の一般常識を反映している。つまり、7世紀の東アジアでは、「日本」は、中国からみた極東を指す一般的な表現にすぎなかった。この日本を国号に用いることは、中国を中心とした世界観を受け入れることになる。……
「日本」は国号の変更を申し出て、それを則天武后が承認した。朝貢国であるからには、国号を勝手に変更することはできない。そのため、皇帝の裁可を仰いだのである。ここに、中華たる唐(周)に朝貢する「日本」という図式が定まる。決して唐への対等、優越を主張するためではなかった。